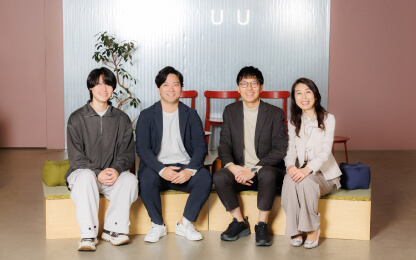INDEX
INDEX
新宿西口エリアの開発に伴い、40年の歴史に幕を閉じる「新宿ミロード」では、2025年3月16日の閉館に向け、現在さまざまなメモリアルイベントが実施されています。
その新宿ミロードをはじめとして、小田急沿線の商業施設の開発や管理・運営を担う㈱小田急SCディベロップメントでは、いかにして顧客とのつながりや地域との結びつきを育んできたのか。
今回は、全社的なマーケティングを担当する齋藤朱莉さん、新宿ミロードの販促や企画に関わる大谷実菜さんに、同社が大切にしていること、今後も大切にしたいことについてうかがいました。
「駅」を起点とした商業施設の管理・運営
小田急SCディベロップメントが管理・運営する商業施設(以下、「SC」)は、小田急線の駅ナカや駅チカの立地がメイン。小田急線利用者や沿線住民へのマーケティングをもとに、入居する店舗の選定やイベントの企画などを行っています。
(齋藤)当社が運営するSCには大きく分けて3種類あります。一つ目は大型の商業施設で、新宿ミロードや相模大野ステーションスクエア、本厚木ミロードのほか、アウトモール型のSCも展開しています。二つ目は駅構内の施設で、下北沢駅の「シモキタエキウエ」や、複数駅に展開する小田急マルシェなどで、より鉄道利用者の方の利便性や日々の生活に寄り添った店舗をそろえています。三つ目は沿線外の物件で、その第1弾として、鵠沼海浜公園(神奈川県藤沢市)のリニューアルに伴い、2024年6月、園内にオープンした「HUG-RIDE PARK」の運営に携わっています。

(大谷)商圏やターゲティングは施設によっても異なりますが、基本的には沿線住民の方や駅利用者を主なターゲットとしています。地域の皆さんや駅を利用される方々に愛着を持ってもらいたいという思いから、施設の屋号はあえて統一せず、地域に根差した施設づくりを目指しています。

寄り添い、包み込む、顧客との関係づくり
SCを訪れるお客さまとの関係構築を考え続けてきた二人に、小田急のSCの魅力や、その源泉に何があるのかを尋ねてみました。
(齋藤)「地域」への目線ですね。入社当時に配属された本厚木ミロードでは、地元の店舗が出店していたり、催事をしたりといったケースが他のSCよりも多かったんです。それは当社が地域に愛着を持ち、地域にフォーカスしてきたからだと思います。また、館内の「AGORA Hon-atsugi」というシェアオフィス&コワーキングスペースでは起業家支援を行っていますが、その出身者がテナントとして出店してくださるなど、地域の方と一緒に施設をつくっていこうという意識は一段と 強いと感じます。

(大谷)新宿ミロードに限らず、「小田急らしさ」を感じるのは、まちやお客さまに寄り添う姿勢かなと思っています。例えば駅前のファッションビルだと、違う駅の施設でも同じお店が入っていることも多いですよね。それも安心感があり魅力の一つなのですが、小田急の場合はエリア特性やお客さまのニーズを取り入れ、場所によってよりデイリーユースな店舗をそろえたり、ファッション感度の高い方向けにしたりと、立地を考慮したSCづくりをしているんです。それはやっぱり、お客さまが求めているものに寄り添って価値を提供し、関係をつくっていきたいという思いの表れだと思います。新宿ミロードもそうで、開業当時から大切にしてきた「“好き”に寄り添う」という姿勢をずっと貫いてきました。がんばって流行を追うだけではなく、少し休みたいとか、今日はゆっくりしたいとか、そんな気分のときにもふらりと立ち寄れる。そんな誰彼問わず包み込むような居心地が、新宿ミロードの唯一無二の価値だと思います。
新宿ミロードが3月に閉館。現在の心境は?
その新宿ミロードの閉館まであと少し。二人は今、何を思い、どんな気持ちで日々を過ごしているのでしょうか。
(大谷)昨年9月にニュースリリースを出してからは、いよいよという実感が強まっています。私たちは閉館のその日までミロードにいますが、「訪れるのは今日が最後」というお客さまもいらっしゃるはずなので、一人ひとりのお客さまに感謝しながら過ごしています。
(齋藤)私にとっても、新宿ミロードは思い出の多い場所ですし、新宿の象徴的なSCの一つです。リリースを出してからはメディアからの問い合わせも多く、やはり多くの人の思い出に残っている施設なんだなと感じることが多いです。


新宿ミロードの閉館は、新たに生まれ変わる新宿駅西口エリアの開発プロジェクトの一環。そこに未来があるからこそ、後ろ向きなムードにはしたくなかったといいます。そのために、リリースと同時に「Good bye Movie」というショート動画を公開。新宿ミロードの思い出を懐かしむ声や、未来への思いなど、SNSでもさまざまな反響がありました。
(大谷)新宿ミロードが大切にしてきた「好き」を応援する気持ちを、このムービーにも込めました。ファッションは40年間で変わっても、そこにはお客さまそれぞれの「好き」があり、そこに寄り添う40年間だったと思います。閉館に対してネガティブな捉え方をされることもほとんどなく、私たちの思いが届いてよかったなと安心しています。
商業施設を通して、地域と共生する企業へ
小田急SCディベロップメントでは、「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を地域共生ステートメントに掲げ、その体現に取り組んでいます。
(齋藤)小田急のSCといえば、やっぱり「駅に近い立地」。また、「エキチカ」であるだけでなく、街とそこに暮らす人々に近づき寄り添う「マチチカ」「ヒトチカ」の視点で、地域と共創しながら新しい価値を生み出していくため、2022年12月にこのステートメントが策定されました。このステートメントをもとにした「Re:born」というプロジェクトもスタートしています。各SCでお客さまから不要な衣料品などを回収し、協力企業に査定していただき、その金額をもとに地域の子どもたちにギフトを贈るというもので、とても好評をいただけています。
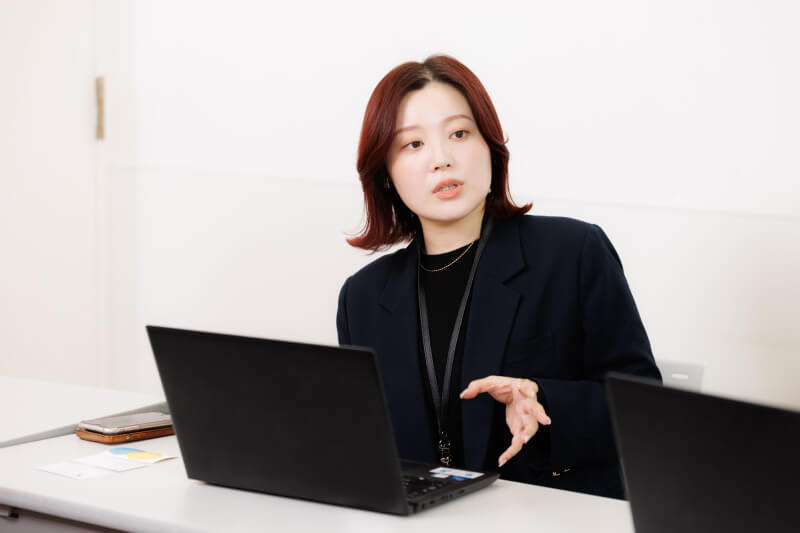
(大谷)新宿ミロードの場合、他のSCと比べるとどうしても近隣在住者の割合が下がるので、「新宿までわざわざ不要品を持ってきていただけるだろうか」と不安もありましたが、ふたを開けてみると想像以上の反響があって驚きました。サステナブルに関するお客さまの関心の高さを知るきっかけになりましたし、新宿でも地域共生ステートメントの実現や、地域とのつながりづくりは可能だと気づけました。


未来に向けた動きは、いっそう活発化する様相です。
(大谷)沿線外への進出は今後注力していきたい事業の一つです。その際、私たちがやる「意味」をしっかりと意識し、「このエリアはこうだから」「小田急のカラーはこうだから」といった固定観念にとらわれすぎずに、これまで通りそこの方々と一緒に、寄り添いながらつくり上げていく姿勢を大切にしていきたいと考えています。

(齋藤)地域への目線は変わらず大切にしたいですね。SCにいらっしゃる方、出店店舗さん、地域の企業や学校、行政、全てをお客さまと捉えて、その地域に提供できる価値を考え続け、実践していくことが、私たちの使命だと感じています。
これからも、小田急の新たなSCが生まれることでしょう。それが小田急沿線であっても、別の地域でもあっても、地域に寄り添い、地域と共生していく。長年にわたり培ってきたその揺るぎない思いこそが、SCづくりの根幹となっています。
※内容は取材時のものです。