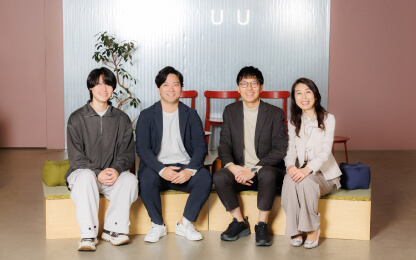INDEX
INDEX
2020年11月に改良工事を終え、「東京の木 多摩産材」をふんだんに使った小田急線の参宮橋駅は、今では周囲の風景にすっかり溶け込んでいます。駅が生まれ変わるまでのストーリーをたどりながら、駅に込める小田急電鉄の思いをひも解きます。
参宮橋駅の「これまで」と「今」
明治神宮、そして代々木公園の最寄り駅である小田急線参宮橋駅。杜と公園の緑は、新宿や原宿、渋谷の「裏」の感じを、より際立たせています。反対の西口周辺には、住宅やオフィスビルが並び、小粋な飲食店なども点在。小高い丘の上にある参宮橋公園に足を運ぶと、都心の喧騒をすっかり忘れさせてくれます。
この環境の良さと向き合い、2018年から2020年までの約2年間にわたり行われた参宮橋駅の改良工事。駅のデザインコンセプトは、「木と緑に溶け込む『杜』の玄関口」です。代々木、山谷などの地名にその名残を留める武蔵野の豊かな自然の記憶と、明治神宮や代々木公園、街路樹や植栽などの周辺緑樹の風景と一体化することを意味しています。
工事期間中は、ともすれば無機質になりがちな工事の仮囲いを、多摩の森林の「木」をモチーフに装飾。あわせて、工事を知らせる看板にも「木」を使い、案内文を木製板面に印刷するなど、工事に対する安心感と新しくなる駅への期待感につながるような工夫を施しました。
そうして完成した駅は、明治神宮の玄関口らしい神社建築をモチーフに垂木や組木などを取り入れ、風格と温もりを感じさせる佇まいとなっています。このインパクトあるデザインは「ウッドデザイン賞2021」(※)にも選ばれました。
※木の良さや価値を再発見できる製品や取り組みについて、特に優れたものを消費者目線で評価し、表彰する制度

地域に寄り添い、親しまれる駅舎に
「参宮橋駅は1923年の開業から長年親しまれていた駅ですが、駅舎の老朽化や明治神宮方面へのアクセス向上が課題でした」と、駅工事を管轄する糟谷拓海さんはそう話します。
明治神宮、代々木公園を目の前にしながら改札口は反対側の西口のみで、行きづらさがあったのも事実です。そこで、東口に改札を設置し、杜の玄関口として分かりやすく、使いやすいように改修しました。一方、西口はまちの玄関口として改札前の空間を広げ、ベンチや案内板を設置しました。

「明治神宮に訪れる方や地域の方が、この駅を通して、この場所に誇りや愛着を持ってもらえるきっかけを提供できればと思っています」と糟谷さんは続けます。
明治神宮をふと意識したり、木の温かみやぬくもりをふと感じたり。「神社建築」をモチーフにした駅は、地域とのつながりをとても大切にしたものです。
参宮橋駅に使っている「木」は「多摩産材」と呼ばれる木材。東京都内の多摩地域で育った樹木から生産した木材のことです。その中でも、多摩産材認証協議会により産地証明された「認証材(東京の木 多摩産材)」を使用しています。これは、多摩地域の適正に管理された森林から生産され、産地証明がされていることを意味します。

東京の木である多摩産材の活用を通じて、東京の地場産業の活性化にもつなげることができる。参宮橋駅は、そんな「東京の自然のつながり」を利用者やまちと分かち合う、サステナブルな社会の実現に向けたメッセージでもあります。
サステナビリティを体現する場所へ
自然との共生を図り、SDGsやカーボンニュートラルへの配慮が欠かせない今、小田急グループでは、美しい地球環境と優しい社会を未来の世代に引き継ぐことを使命としていますが、企業単独で実行できるほど簡単なものではありません。
参宮橋駅の改良工事完了後には、子ども向けに木材を身近に感じることができるワークショップを行いました。また、近隣の文化学園大学と連携し、在学生を対象に、建築・インテリアデザインをテーマにした駅見学授業も継続的に行っています。
こうした木のにおいや触り心地を実感できる機会や、日光や雨に影響を受けやすい木材の特徴と生かし方を学ぶ機会をつくることで、多摩産材を通して、サステナビリティを一緒に考える場としました。


「日常の中で、駅で待つ時間が心地よいと感じたり、木組みのデザインを見てふと明治神宮の存在を意識したり、そんな一瞬をつくることができれば嬉しいです」と糟谷さん。「くらしと密接な関係にある駅だからこそ、地域の多様な視点を設計に取り入れる。そんな駅づくりを考えていきたいですね」
現在、改良工事を進む鶴川駅でも、利用者や地域に寄り添い、地域や社会の課題解決に応える、愛される駅を目指しています。
※内容は取材時のものです。