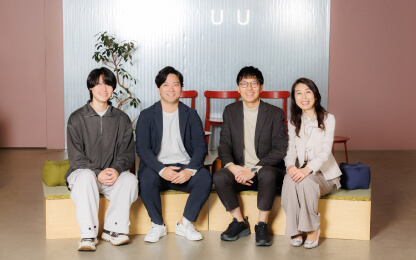INDEX
INDEX
駅係員は駅を利用するお客さまから「乗り換えは?」「出口は?」「トイレは?」など、さまざまな質問をいただきます。こうした際の対応はお客さまの安心につながる大切な業務の一つであり、なかでも運行異常時の対応はその最たるものです。電車が遅れた時、運転を見合わせた時、お客さまが一番知りたい情報をスピーディかつ正確に伝えるための取り組みについて紹介します。
全70駅の接遇レベルの向上を目指して
小田急電鉄㈱では、「日本一安全な鉄道をめざします」という基本理念のもとに、お客さまに安心して鉄道をご利用いただくための的確なアナウンスやお声がけに努めています。
とりわけ、駅で直接お客さまに応対する駅係員は、これまでにも競技形式で行われる「接客グランプリ」をはじめ接客意識や接客スキルの向上を目的としたさまざまな取り組みを行ってきました。
その一つに、管区(※)ごとに実践しているサービス向上の取り組みがあります。小田急線の主要な駅には、サービス向上の中心的役割を担うサービスリーダーがいます。外部講師による研修や、各管区のリーダー、同業他社との情報交換などを定期的に行い、そこで得たスキルを持ち帰り、所属員にフィードバックし業務に生かすことで、全70駅のサービスレベル向上を図ってきました。
※複数の駅を束ねる管理区分のこと

一方で、駅係員に求められるサービスの役割や対応に絶対的な形はなく、時代に合わせて変化するものでもあります。例えば、スマートフォンで簡単に情報収集ができるようになったおかげで、駅係員がお客さまに道案内をするケースは大きく減少しました。
真価が問われる運行異常時の対応力
こうした中で、駅係員の対応力が最も問われるのは、「運行異常が発生したとき」です。小田急総合研究所が行ったアンケート調査「小田急沿線生活者1万人調査」によると、異常時案内の重視度は高い結果となり、利用者のニーズもうかがえます。
小田急電鉄で駅係員の教育を担当している三澤洋子さんは次のように話します。
「急速にSNSが広がっていく中で、鉄道の運行に関する情報も瞬く間に拡散し、場合によっては駅係員よりも先にお客さまが運休情報を知っているというケースもありました。こうしたこともあり、運行異常時こそ、よりスムーズにお客さまに情報を伝達する必要があると痛感しました」
情報連携の強化で利用者にさらなる安心を
そのために立ち上がった新たな取り組みが、「サービス・信号取扱い合同研究会」です。これは、改札やホームでお客さまと直接やり取りをする駅係員と、信号機やポイントを操作しダイヤ乱れを防ぎ、解消させる係員である信号扱者の連携を目的にしたものです。信号扱者は電車の運行に支障があった際、いち早く状況を把握することができる立場にいるため、駅係員と連携することで、素早く、正確にお客さまに運行情報を伝えることができます。

「信号扱者には、運行異常時の初期対応や定時運転への早期回復を目的として異常時対応の訓練や研究を実施してきましたが、この合同研究会では正確な情報をどう提供していくかを考えています。車内警報ブザーが操作された時や踏切内での自動車の立ち往生、沿線火災の発生などさまざまある中で、各管区の特性を踏まえたリアルに近い設定でロールプレイングを行い、駅係員と信号扱者がお互いに連携を取りながら異常時の行動をシミュレーションして、対応力に磨きをかけています」(小田急電鉄 旅客営業部 嘉山裕子さん)

鉄道に求められるニーズは、世の中の動きによって今後も変化することでしょう。一方で、運行異常時の対応力は時代の流れに関わらず培う必要があります。変わるものと変わらないもの。どちらにも臨機応変に対応できるよう、各駅ではこれからも接客スキルや対応力の向上の取り組みを継続していきます。そして、現場で対応する係員たちの声を生かし、これからも安全で安心な運行に励んでいきます。
※内容は取材時のものです。