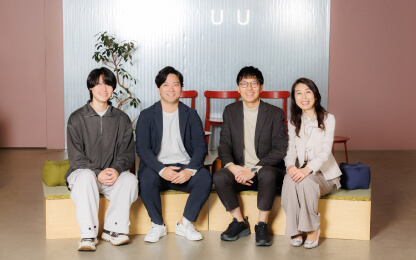INDEX
INDEX
気候変動や環境破壊により、地球の姿は刻々と変化し続けています。当たり前のような日常生活も、時に旅に出かけて、美しい景色を眺め、おいしいものを食べるような楽しみもできなくなってしまうことが絵空事ではありません。
この地球を次代に引き継ぐためにできることは何か。
小田急電鉄㈱では、その第一歩としてサーキュラーエコノミー(循環型経済)を通じた豊かなくらしづくりにチャレンジし、「ごみのない世界」を目指す取り組みを進めています。
日々、多くのお客さまにご利用いただいている鉄道サービスを中心に地域に根差した事業を展開し、ごみを多く扱う立場でもあるからこそ、ごみを少しでも減らすことができないか。そんな意識の高まりから2021年から始動したのが、ウェイストマネジメント事業「WOOMS(ウームス)」です。
この事業に携わる小田急電鉄の正木弾さん、井上直輝さん、日置順子さんに、ごみのない豊かなくらしづくりに向けた思いをうかがいました。
くらしづくりを事業の根幹とする自分たちにできること
「私たちは長年、鉄道というインフラに加え、生活に身近な商業施設の運営などを通じて、お客さまの『くらし』の一部を担ってきました。そうした観点で捉えると、くらしを脅かす気候問題や資源の枯渇などによる地球規模の危機は決して他人事ではありません。WOOMSという事業を通してごみ収集に携わる皆さんの役に立つような取り組みや改善を続け、子どもたちにきれいな地球を残していくことは私たちの責任であると考えています。だからこそ、サーキュラーエコノミーへの移行は必須の課題です」
立ち上げ段階からこの事業に携わる統括リーダーの正木さんは、事業への思いをそう話します。ごみ問題に取り組むことになった経緯については、「小田急電鉄の中で循環型社会に向けた取り組みを模索していたことがきっかけだった」と言います。その過程で「ごみ」という課題が浮かび上がってきました。
「そこで、自治体や商業施設で廃棄物の収集や処理に関わる人に話を聞いてみると、まずは私たち小田急電鉄こそが地域で一定規模のごみを出す排出者であることに気付かされました。また、資源をきちんと分別したくてもごみ処理場が遠い、コストがかかりすぎるといったケース、排出量が少ない小規模店舗では収集事業者から収集を断られるケースもあると知りました」(正木さん)

実際に座間市でごみ収集車(以下、収集車)に乗せてもらううちに見えてきた実態は、「運ぶこと」の難しさでした。日々排出されるごみは排出量をコントロールしにくい上に、収集ルートごとに細かなルールがあるなど属人化している点も多く、担い手も不足しています。
「街はごみを蓄え続けられる構造ではないので、絶えず収集・処理する必要があります。ごみがあふれてしまったら、地域の価値も大きく下がってしまう。まちづくりやくらしづくりを事業の根幹としてきた私たちとしても、何かしなければならないと危機感を抱き、テクノロジーソリューションの開発に着手しました」(正木さん)
ごみ収集という仕事の見方や意識が変わる
こうして、自治体や民間の収集事業者に向けたアプリを開発。収集車ごとにタブレット端末を設置し、最適な収集ルートの生成や収集の進捗管理などを可能にしました。さらに、余力のある収集車が他のルートへ入って収集をサポートする機能なども搭載し、より効率的なごみ収集を実現させています。

すでに効果も表れています。2024年度に実証事業を行った宮城県仙台市では、収集車1台のごみ処理場へごみを運ぶ回数が1日あたり平均4.3回から3.7回に減少。また、他の収集車のサポートができる機能を活用したことで、収集にかかる時間も短縮されました。
導入前後のサポートやフォローを担当する井上さんに導入前後の変化について尋ねてみました。
「収集事業者へのアンケートでは、収集の遅延やごみの取り忘れがなくなったという声をいただき、またこれまでは収集スタッフの経験に頼っていたルート把握なども、デジタル化したことで共有しやすくなり、OJTだけに頼らない教育が可能になったという声もありました。みんなでルートを共有できることで、『この人の担当ルートは収集ポイントが多い』といったような情報も見えるようになり、ルートの改善に関する議論も活発になったと聞いています」

さらに、収集スタッフの方から「仕事のやりがいが増した」といううれしい声もあったと言います。
「WOOMSの立ち上げ期から導入いただいている神奈川県座間市でも、6割以上の方が『仕事のやりがいが高まった』と回答しています。今まで収集スタッフが個別で把握していた収集作業が可視化され、助け合える仕組みができたことで、チームで仕事をしている意識や、自分が職場の改善活動に参加できているという実感が得やすくなったためだと考えています」(正木さん)
循環型社会実現への第一歩は共感と参加から
座間市では収集効率が上がったことで収集車全体の余力ができ、これまでは可燃ごみとしていた剪定枝(庭木の手入れなどで出る木の枝)を新たに資源として回収できるようになりました。WOOMSが目指すのは、この「創出された余力でできることを見つけて実行する」こと。ごみ収集の効率化を通して、地域住民も巻き込んだ循環型社会実現への取り組みも進んでいます。
「座間市とはコンポストバッグを使った生ごみの削減と堆肥化にも取り組んでいます」と語るのは、WOOMS共創コーディネーターの日置さん。座間市内の約600世帯に専用のバッグと生ごみと混ぜ合わせる原料を配布し、家庭から出る生ごみを堆肥(コンポスト)にしてもらう「フードサイクルプロジェクト」を行っています。

コンポストバッグには合計20kgの生ごみが投入可能なため、その分のごみ減量が可能に。
「生ごみはほとんどが水分で、可燃ごみの袋が重くなるのもこの水分のためです。生ごみを堆肥にしてごみとして排出しないことで、環境負担の軽減とともに収集スタッフの身体的な負担も減らせます。各家庭で作られた堆肥は収集車が巡回して回収し、畑へ運びます。一人ひとりにできることは小さくても、地域や行政が関わることで大きな変化につながっていくはずです。フードサイクルを通してそのことを知ってもらい、子どもたちにも環境への配慮の大切さを知ってほしい。コンポストバッグがさらに普及していけば、生ごみを堆肥にして畑へ送り、そこでできた食材をいただいて……という循環も可能になります」(日置さん)
このコンポストバッグを通じた資源循環のように、デジタルサービスの開発だけでなく、コミュニティとつながり包括的にごみ処理の解決に取り組んだことが評価され、2024年の「グッドデザイン金賞」も受賞しました。


地域で暮らす一人ひとりの小さな取り組みから生まれる意識の変化、収集にあたるスタッフの働きやすさや仕事のやりがい醸成、そして、何よりもきれいな地球を未来の子どもたちに残していきたい。三者三様の「ゆたかなくらし」がありますが、共通しているのは「地域への思い」。ごみ収集の効率化という一つの切り口から生まれる変化と、その先にある循環型社会、そこに住まう人々の「ゆたかなくらし」の実現に向けて、小田急電鉄とWOOMSは一歩を踏み出したところです。

※内容は取材時のものです。