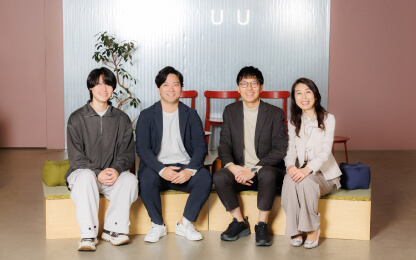INDEX
INDEX
少子高齢化や人口減少による働き手不足が今、社会課題として浮き彫りになっています。そうした中で、私たちが日々当たり前に享受しているサービスを支える働き手の確保や、新たな技術などによってそれらをカバーする動きが急務です。
小田急グループのバス事業者である神奈川中央交通(以下、神奈中)が取り組む、路線バスの自動運転化もその一つです。バス運転士の不足や、それに起因するバスの減便に伴うサービス水準の低下は、市民生活にも大きな影響を及ぼします。そこで、行政やビジネスパートナーと手を組み、自動運転化の実証実験、実装に向けた動きが活発化しています。
今回は、神奈中で自動運転をはじめとする技術革新に取り組む次世代モビリティ担当の富永勇輝さん、連携する平塚市まちづくり政策部 交通政策課の平宮巧さん、広永倫明さんに、自動運転化に向けた手応えや進捗、さらにこれらの技術導入によってどのような形で地域のゆたかなくらしに寄与していきたいのか、その思いを聞きました。
輸送サービス水準の維持。その「手段」としての自動運転
神奈中が自動運転に取り組み始めたのは2017年ごろのこと。運転士不足が見込まれ、このままでは路線形態やサービス水準に影響が出てしまうのではと危機感を抱き、どうすれば持続可能なモビリティ(移動方法)サービスを提供できるかを考えるようになったと富永さんは語ります。
「実際に運転士の減少や働き方改革を受けて、ダイヤの変更や減便をせざるを得ない路線も出てきていました。ですが、お客さまの中には『バスがないと出かけられない』という方も少なからずいらっしゃいます。自宅から『最初の一歩』を踏み出すための手段であるバスを、どうすれば維持できるのか。その一つの選択肢として自動運転に目を向けました」

一方、バス事業などを通して、日ごろから神奈中との交流も深い平塚市まちづくり政策部で交通政策を担当する平宮さんは、市のバス交通事情について次のように話します。
「平塚市は人口約25万人に対し、鉄道駅がJR平塚駅のみという珍しい地域です。そのため市内には約70系統の路線バス網が発達しており、バスが市民の皆さんの足として重要な役割を果たしています。運転士不足によるバス交通への影響は市としても大きな課題と認識していて、その解決の一助として、神奈中さんとともに自動運転化に取り組む意義を感じています」
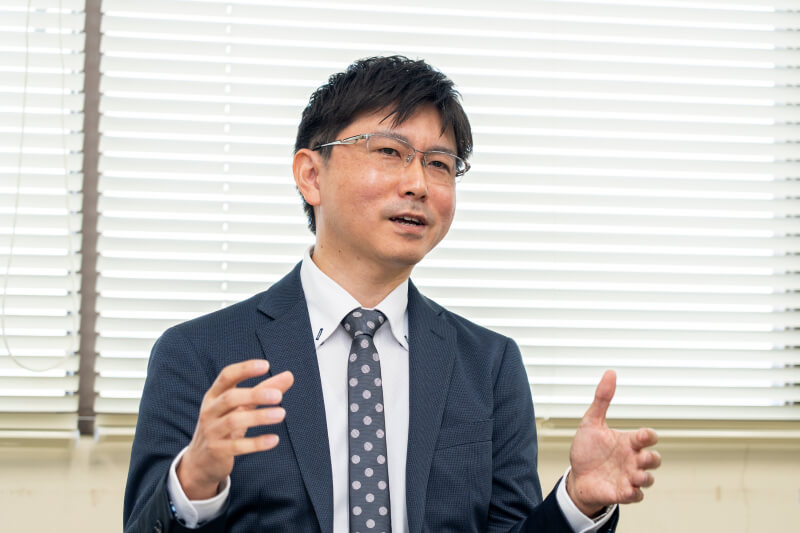
市内を網の目のように走る神奈中バスは不可欠な公共交通であり、サービス水準の低下は市民生活や地域のにぎわい創出にも直結するもの。こうして、バス事業者と行政によるバス路線の維持確保に向けた両者の取り組みが動き出すこととなりました。
官民の「共創」。平塚という場所から発信することの意味
今回の路線バスの自動運転化に関する取り組みの特色を富永さんはこう話します。
「実証実験には、連携協定を組んだ自動車メーカーが提供する大型バスを使用しています。さらに、実証実験のためのルートではなく、既存のバス路線そのままの自動運転化を目指している点では、全国的に見ても珍しい取り組みではないでしょうか」

平塚市ではこれまでに2回の実証実験を行い、国が定める自動運転レベル2(アクセルとブレーキ、ハンドル操作を部分的かつ持続的に自動化)での路線バス運行を実施。このうち、2回目の実証実験では周辺住民の方を中心とした一般試乗会も行い、バスに同乗した広永さんは市民の反応に自動運転への期待の高まりを感じたと言います。

「市では2027年に一路線で自動運転レベル4(特定条件下で全ての運転操作を自動化)での運行を目指しており、将来的には住宅街が広がる平塚駅南口エリア全体の路線バスの自動化も見据えています。『自動運転バスだ』と声をかけていただくことも増えましたし、一般試乗会に参加された方にはご家族連れも多く、広く関心を持っていただいているなと感じました。一般の方も試乗ができるようになったことで、いよいよと感じてくださる方が増えた印象です」

富永さんも、「駅前での自動運転バスの待機場の確保や、市民への周知においても平塚市さんの熱意や協力が大きな推進力となりました。また、お客さまからも『地元でこうした取り組みが行われているのがうれしい』といった声をいただき、モビリティサービスの持続可能性を示す一つのモデルケースを平塚市から発信することの思いを強くしました。そして何より、本社を構える私たちの本拠地とも言えるこの地でこうした取り組みに挑戦できたことは、自分たちの仕事が地域の活性化に結び付いているという実感を得られたと同時に、モチベーションにもつながりました」とここまでの成果を振り返ります。
理想は、当たり前のものとして地域に溶け込むこと
実証実験での確かな手応えを感じつつも、自動運転技術のさらなる向上は乗り越えるべき大きな課題です。
「バスの自動走行については一定のレベルに達しつつあり、目標とする自動運転レベル4に向けても着実に進歩を重ねています。一方で、現状ではドアの開閉や運賃の収受、お一人での乗降が難しい方へのお手伝いなど、普段運転士が行っている対応も数多くあります。これらをどこまで自動化するのか。また、病院や公共施設があるエリアなど運転士が必要になるであろう路線を見極め、サービス運営のあり方を考えていく必要があります。バス路線全てを自動化するのではなく、今後ますます貴重になっていく運転士の存在を最大限生かしていくための一つの手段であるという前提は大切にしていきたいですね」(富永さん)
また、自動運転の実現には市民のさらなる理解や関心の向上、ときには行政の垣根を越えた連携も必要になってきます。
「路上駐車を減らすためのマナー啓発をはじめ、自動運転バスの導入に対する興味喚起や理解醸成のため、市報や市内施設への掲示、企業や学校への周知など、さまざまな形で取り組んでいるところです」(平宮さん)
「今回の取り組みを通じて、部署間でも交通課題に関する情報共有の強化を図っています。また、平塚市単独ではなく、例えば同じような交通課題を抱える他市などとも連携し、市民生活に欠かせないバスというものをどうやって維持していくのか、一緒に考えていくことが重要だと考えています」(広永さん)
最後に、富永さんに地域にとってこんな存在になれればという将来像を聞きました。
「神奈川県内で100年以上にわたってバス事業を展開してきた会社として、地域の皆さんに『神奈中があってよかった』と愛していただけるような、当たり前にある存在としてまちに溶け込んでいたいと思っています。自動運転バスも、最終的には『あ、自動運転バスだ!』と言われることがなくなるのが理想かもしれません。そのために、より多くの方に自動運転バスに触れてもらう機会をつくることができたらと考えています」
バスを利用する人や地域の方々が、これからも変わらずにバスを利用して、これまでと同じように生活を続けられること。それこそが、神奈中や平塚市が目指す「ゆたかなくらし」の形と言えるでしょう。

※内容は取材時のものです。