安全のスキルアップ
安全のスキルアップとヒューマンエラー防止に努めています。
安全のスキルアップとヒューマンエラー防止のために、経営層から現業係員まで職位に合わせた適切な安全教育プログラムを組んでいます。また、安全意識を高め、維持・継承していくには、過去の鉄道事故や輸送障害を憂い、その悲惨さや心の痛みを忘れることなく伝えていくことも重要であるとの認識から、鉄道人としての心の形成も踏まえた安全教育体系の整備を進めています。
主なプログラム
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| コンセプト教育 | 経営層から監督者層(現業長)を対象に、運輸安全マネジメントの趣旨について学ぶ |
| ヒューマンエラーマネジメント教育 | 管理者層(課長・課長代理)から監督者層を対象に、ヒューマンエラーを発生させにくい職場運営を学ぶ |
| 安全意識向上教育(安全講演会など) | 安全にかかわる部門の全社員を対象に、強い安全意識を啓発する |
| 技能教育 | 各部門・各職場において、必要な技能を教育する |
| その他 | 係員層を対象とした「技能伝承力向上研修」「他職場体験研修」など |
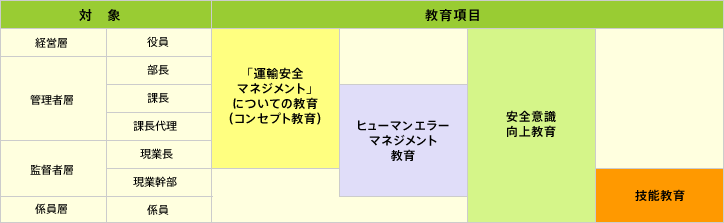
技能伝承に取り組んでいます。
鉄道の安全性の向上に伴い、脱線などの異例事故が発生することはほとんどなくなりました。
そのため、係員がそのような事故や対応・復旧作業を経験する機会も少なくなったほか、業務の外部委託化などの影響もあり、異常時における対応能力や技術・技能の維持が課題となっています。


そのため、万が一、前述のような事故が発生した際、迅速かつ的確な対応が取れるよう、技術の伝承と技術力の向上を目的に、それぞれの職種に応じた教育や訓練などを実施しているほか、「技能伝承力向上研修」を開催しています。


各部の主な教育・訓練
| 部門 | 目的 | 訓練名 |
|---|---|---|
| 運転車両部(運転担当) | 迅速、的確な対応による併発事故防止と支障時分の短縮 | 異常時対応競技会 |
| 異常時におけるお客さまおよび公衆へのご案内向上 | ||
| 関係係員相互間の安全確保と情報伝達 | ||
| 運転車両部(車両担当) | 脱線復旧作業時の知識習得と技能向上 | 車両3区所合同訓練 |
| 旅客営業部 | 異常時における関係職場の連携体制の強化 | 異常時対応研究会 |
| 係員の作業分担の明確化と事故情報の共有化 | ||
| 運行異常時における信号駅扱い対応の技能向上 | 全線駅扱い訓練 | |
| 異常時対応能力向上 | 若手信号扱者訓練 | |
| 工務部 | 保線重機械脱線時における早期復旧 | 保線重機械脱線復旧訓練 |
| 異常時における正確・迅速な情報の伝達 | 情報伝達訓練 | |
| 業務知識・技能の習得と実務レベル差解消 | 保線実務教育 | |
| 電気部 | 検査、補修業務における技術力向上 | グループ別の技術競技会 |
| 複々線建設部 | 地下化工事区間の連絡通報体制の確認 | 無線通話訓練 |
事故の風化防止に取り組んでいます。
ベテラン社員が培った知識や技能を、後輩たちに確実に伝承し、若手社員の知識・技術力を向上させることが、すべての職場で課題となっていることから、安全文化の醸成を目的に実施している「輸送の安全講演会」「安全シンポジウム」や「事故事例DVD製作」のほか、各部門でもさまざまな取り組みを行っています。
| 部門 | 内容 |
|---|---|
| 運転車両部(運転担当) | 東海大学前駅での鉄道人身障害事故の発生日を「教訓の日」と定めて、事故の風化防止を図るとともに、絶対に同種事故を再発させないため、ミーティング・対話を通じ所属員への教育を実施しました。 |
| 運転車両部(車両担当) | 大野総合車両所に、後世に伝承すべき事故を「事故事例パネル」にして展示し、若年者教育などに活用しているほか、他職場からの見学にも活用しています。 |
| 旅客営業部 | OTC(小田急型列車運行管理システム)導入以前に教育を受けた信号扱者OB社員から、過去の事故体験談や事故防止に対する信条、心構えなどを伺う講話を実施しました。 |
| 工務部 | 「事故防止の日」「労災防止の日」など過去の事故や災害を振り返る日を設け、「事例研究」などを実施しました。 |
| 電気部 | 「電気部事故防止フォーラム」や事故資料集を活用した事例研究を実施しました。 |
| 複々線建設部 | 鉄道工事の特殊性の浸透と過去の事故事例に学ぶため「事故防止の日」を定めているほか、資材・施設の点検のため安全パトロールを月1回開催し、事故体験などを水平展開しました。 |
| 人事部 | 乗務員養成課程において、他社の重大事故事例などを収録した視聴覚教材を使用した教育や、他社の事故展示室の見学、当社OBによる事故の体験談を聞く機会など、重大事故に学ぶ教育をカリキュラムに取り入れています。 |
科学的分析力向上に取り組んでいます。
「2011年度重点取り組み事項」の一つ、「科学的分析手法の導入など、背後要因の分析力向上」について、各部門では業務の特性を踏まえた独自の分析手法を導入し、事故などの背後要因や発生傾向を分析し、対策の検討、実施につなげています。
| 部門 | 内容 |
|---|---|
| 運転車両部(運転担当) | 「m-SHELモデル」(事故の背景について、ハードウェア、ソフトウェア、環境、関係者、マネジメントの側面から分析する手法)を基に、業務特性に応じ改善を加えた「小田急型事故分析シート」を開発し、背後要因や発生傾向を分析し、取扱い不良(ATS動作の現象など)の減少に向けた対策の検討、実施に取り組んでいます。 |
| 運転車両部(車両担当) | 「小田急型事故分析シート」を活用し、戸袋への引き込み事象に対する分析を行い、発生抑制および列車運行の支障時分の短縮に向けたハード対策の検討、実施に取り組んでいます。また、大野総合車両所の親子見学会などの一般向けイベントでは、戸袋への引き込み防止の啓発活動を実施しています。 |
| 旅客営業部 | 運転車両部で運用している「小田急型事故分析シート」を参考に、業務特性に応じ改善を加えた「旅客営業部型事故分析シート」を開発し、信号扱者の信号操作のミスの発生傾向を分析し、分析結果を踏まえた訓練、対策を実施しています。 |
| 電気部 | 「m-SHELモデル」をベースに、業務特性に応じた独自の分析手法「電気部型事故分析手法」を開発し、ヒューマンエラーの背後要因や発生傾向を分析し、対策の検討、実施に取り組んでいます。 |



