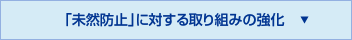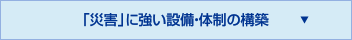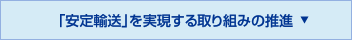安全管理体制の推進
以下、安全重点施策の4項目に沿って、2016年度の主な取り組みを紹介します。
強靭かつ柔軟な「現場力」の構築
安全文化の醸成を図っています。
安全・安定輸送を絶え間なく実践するためには、全社一体となった安全文化が必要です。安全文化の醸成のために、当社では2008年度より、10月1日を「鉄道安全の日」と制定しています。
(1) 職場巡視

定期的に、社長、安全統括管理者、交通サービス事業本部内の各部長が「職場巡視」を行っています。経営管理者と現業係員がコミュニケーションを図ることで十分な意思疎通を行い、安全文化の醸成を常日ごろから図るものです。
(2) 安全シンポジウム/輸送の安全講演会


2016年10月4日に「安全シンポジウム」を、同年10月11~13日に「輸送の安全講演会」を開催しました。
これは、鉄道輸送に係る従業員の安全意識の継続的高揚を図ることを目的としたもので、「安全シンポジウム」を大野地区で、「輸送の安全講演会」を大野地区、小田原地区、藤沢地区でそれぞれ開催しました。
安全シンポジウムでは、「強靭かつ柔軟な現場力」を構築するため、「状況の変化を自ら判断し、適切に対処する手法(レジリエンス)」をテーマに、外部講師をお招きしてご講演いただきました。このシンポジウムには、社長、安全統括管理者以下の当社社員をはじめグループ各社の従業員など約320名が参加しました。
輸送の安全講演会では、「一人ひとりが創る安全、築く信頼」をテーマに、「お客さまに安全・安心と喜び・感動を与える現場での手法」と題して、外部講師をお招きしてご講演いただきました。この講演会では3日間で約900名が聴講しました。この講演は同じテーマで3年間継続して開催し、鉄道輸送にかかわる全従業員が聴講することを予定しています。
(3) エリアミーティング


現業係員および職場間相互のコミュニケーションの向上を目的に、「エリアミーティング」を実施しています。各職場から選出された上位職のメンバーが自主的にミーティングを行い、その成果について報告会を通じて役員に報告しています。また、若年層を中心とした「職場見学会」では、他職場の業務を体験することにより相互理解を深めています。
異常時を想定した、さまざまな訓練を実施しています。
いつ起こりうるか分からない異常時を想定し、さまざまな訓練を実施しました。訓練後には関係者を含めた反省会を行い、その効果の検証や改善点などについて意見交換し、取り扱いの見直しや、より効果的な訓練方法の立案などに生かしています。
(1) 総合防災訓練を実施しました。

2016年9月、「大規模鉄道事故事業継続計画(事故BCP)」に基づき、大規模な鉄道事故の発生を想定し、鉄道部門における初動対応・対応方針決定・指示伝達について訓練を行い異常時における対応力の向上を図りました。
今回の訓練では特急列車が脱線転覆、多数の死傷者が発生したことを想定し、鉄道部門で収集した情報により代替バス検討チーム・被害者支援チームを設置、情報収集・整理、対応方針の検討を行いました。
(2) 異常時総合訓練を実施しました。

2016年10月、「異常時総合訓練」を海老名電車基地において警察・消防と合同で実施しました。この訓練は「踏切で電車と乗用車が接触し脱線、多くの負傷者がでている」という想定のもと、事故発生時の初動と復旧対応、警察・消防機関との合同訓練による鉄道災害事故発生時の対応と、現地責任者および活動時の二次災害防止に対する取り扱いを確認しました。
(3) 代替バス輸送訓練を実施しました。

大規模地震や大規模鉄道事故などにより、鉄道を長期間にわたり運休せざるを得ない場合になったことを想定した「代替バス輸送訓練」を2016年11月に実施しました。グループバス会社と合同で、あらかじめ設定されたルートで実際に移動する訓練を実施し、マニュアルで定めた実施手順の確認と課題の検証を行いました。
(4) 鉄道テロ対応訓練を実施しました。

テロによる不測の事態に備えるため、警察・消防・自治体・関係各機関と連携し、さまざまな状況を想定した実践さながらの訓練を行いました。2016年10月に相模大野駅と愛甲石田駅、2017年3月に成城学園前駅にて実施しました。
安全に係る現業職場における部門横断的な取り組みを推進しています。
現業職場間において、「合同訓練」や「職場交流」などの実施を通じて、部門間のコミュニケーションの強化を図っています。
現業職場間の主な取り組み
| 部門 | 主な取り組み |
|---|---|
| 運転車両部(電車区、車掌区) 旅客営業部(駅) |
|
| 運転車両部(運輸司令所) 電気部(電気司令所) |
|
| 運転車両部(電車区) 運転車両部(総合車両所) |
|
| 運転車両部(電車区、車掌区、検車区) 旅客営業部(駅) |
|
安全のスキルアップとヒューマンエラー防止に努めています。
安全のスキルアップとヒューマンエラー防止のために、経営層から現業係員まで職位に合わせた適切な安全教育プログラムを組んでいます。また、安全意識を高め、維持・継承していくには、過去の鉄道事故や輸送障害を憂い、その悲惨さや心の痛みを忘れることなく伝えていくことも重要であるとの認識から、鉄道人としての心の形成も踏まえた安全教育体系の整備を進めています。
主なプログラム
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| 安全意識向上教育 |
|
| コンセプト教育 |
|
| ヒューマンエラー教育 |
|
| 技能教育 |
|
| 鉄道係員養成教育 |
|
●技能伝承に取り組んでいます。
鉄道の安全性の向上に伴い、列車衝突などの事故が発生することはほとんどなくなりました。そのため、係員がそのような事故や対応・復旧作業を経験する機会も少なくなったほか、業務の外部委託化などの影響もあり、異常時における対応能力や技術・技能の維持が課題となっています。
そのため、万が一、前述のような事故が発生しても、迅速かつ的確な対応が取れるよう、技能の伝承と技術力の向上を目的に、それぞれの職種に応じた教育や訓練などを実施しています。



各部の主な教育・訓練
| 部門 | 内容 | 教育・訓練名 |
|---|---|---|
| 運転車両部(運転担当) |
|
異常時対応競技会 |
| 運転車両部(車両担当) |
|
車両3区所合同訓練 |
|
JR東海との合同訓練 | |
|
車両整備技能競技会 | |
| 旅客営業部 |
|
異常時対応研究会 |
|
異常時情報提供教育 | |
| 工務部 |
|
保線重機脱線復旧訓練 |
|
情報伝達訓練 異常時対応訓練 |
|
|
保線実務教育 | |
| 電気部 |
|
技能認定研修 |
|
電気部階層別集合教育 | |
| 複々線建設部 |
|
安全推進協議会 |
|
施工安全確認会 (工事請負会社と実施) |
|
|
緊急連絡訓練 (工事請負会社も含む) |